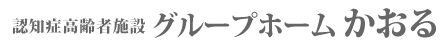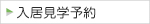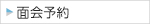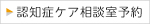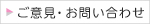健康サポート
病気と治療の基礎知識
脂肪肝

肝臓に中性脂肪がたまった状態を「脂肪肝」と呼びます。脂肪肝の主な原因は、お酒の飲み過ぎ、肥満、食べ過ぎ、糖尿病などの代謝内分泌疾患で、薬剤によって起こることもあります。
脂肪肝になると、食欲不振、吐き気、嘔吐、黄疸などの症状が出ることがありますが、これらは脂肪肝の状態がかなり進んでこないと現れません。脂肪肝の初期には症状から気付くことが少ないため、定期健診などでチェックして早期に発見することが大切です。
では、なぜ脂肪肝は起こるのでしょう。
食べ過ぎで余剰となったカロリーが皮下脂肪と同様に肝臓に蓄積した場合や、肥満によって肝臓自体で脂肪の合成が亢進したり、肝臓と全身の輸送がうまくいかず脂肪が肝臓に集積したりする場合に、脂肪肝となります。また、肝細胞障害や大量のアルコールで脂肪を輸送するたんぱく質の合成がうまくできないときにも、脂肪が肝臓から運び出されず、肝臓に脂肪がたまってしまいます。
一般に脂肪肝は、飲酒習慣のある人に起きる病気と思われがちですが、アルコールを飲まない人に起きる非アルコール性の脂肪肝(NAFLD)もあり、肝硬変に移行するケースもあるので注意が必要です。
脂肪肝の診断では、血液検査でコレステロールや、AST/ALT(GOT/GPT)、γ-GTP、コリンエステラーゼなどの値を測ったり、超音波やCTなどの画像診断を行ったりします。最終的に診断をつけるために、肝臓の組織を微量にとって調べる肝生検という方法をとることもあります。
脂肪肝の治療は、生活習慣を改める努力が第一歩となります。肥満が原因ならば食事療法と運動療法を、飲酒が原因であれば禁酒を行うことで、脂肪肝はかなり改善されます。それでも効果がない場合には、薬物による治療が行われます。ただし、薬物療法はあくまで補助的な治療と位置づけで、生活習慣の改善が何より重要です。
関連リンク
グループホームかおる
住所
〒350-0271
埼玉県坂戸市上吉田260-24
電話番号
049-280-7050
FAX
049-280-7051
交通案内
東武東上線北坂戸駅西口
徒歩10分
駐車場ございます(無料)